鉄鋼素材の種類と特徴を簡単に解説
一般に私たちが日常的に「鉄」として認識しているものは、正確には「鋼鉄」に分類される材料です。
鉄にはこのほかにも多様な種類があり、それぞれ異なる強度や靱性といった特性を有しています。
そのため、用途に応じて適切な種類の鉄を選定する必要があります。鉄道や自動車に代表される工業製品には、多様な種類の鉄鋼が用いられています。
工作機械で加工を行うにあたっては、各素材の特性を正しく理解し、最適な材料選定を行うことが不可欠です。
鉄は、鉄鉱石を原料として製造される金属材料です。鉄鉱石は海底に豊富に存在し、その推定埋蔵量は世界全体で1兆トンを超えるとされています。
その豊富な資源量により、鉄は他の金属に比べて圧倒的に採掘量が多く、金属製品の約80%を鉄が占めています。
加工性に優れることも鉄の大きな特徴であり、高温・常温での圧延、鍛造、引抜きなどによりさまざまな形状への成形が可能です。
また、焼入れや焼もどしといった熱処理により、硬度や靱性の調整ができ、さらなる加工性の向上が図れます。
安価で市場流通性が高いことから、鉄は現代社会において非常に身近で重要な材料です。
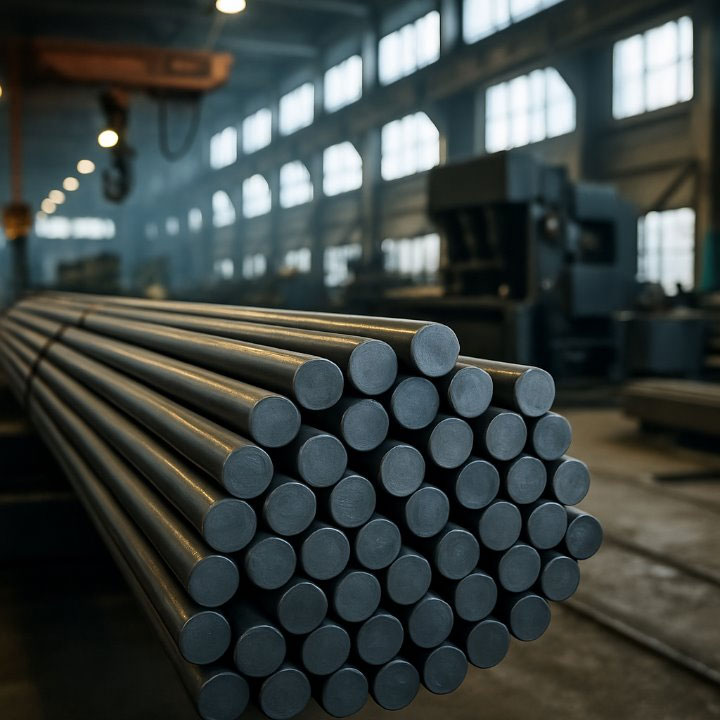
成分で変わる鉄の呼称
鉄のみで構成された純度100%の「純鉄」は、一般的に想像される灰色の鉄とは異なり、白色の光沢を有する外観をしています。
しかし純鉄は、空気中で酸化しやすく、また極めて脆いため、そのままでは工業製品としての利用には適していません。この純鉄に炭素を添加することで、強度や靭性が向上し、「鋼」となります。私たちが日常的に「鉄」と呼んでいるのは、この「鋼」を指します。
鋼は純鉄よりも優れた強度と加工性を持ち、用途に応じて炭素量を調整することで名称や特性が変わります。炭素をほとんど含まないものは「純鉄」、炭素含有量が0.02%〜2.14%のものは「鋼鉄」、そして2.1%〜6.67%と高い炭素量を持つものは「鋳鉄」と分類されます。
炭素量の増加に伴い、鉄は硬度と強度が向上しますが、それに比例して靭性が低下し、脆性が増すため破断しやすくなります。鉄は優れた強度と加工性を備えますが、硬さと靭性を同時に高めることは困難です。
そのため、使用目的に応じて最適な性質の鉄を選択することが重要です。
| | 名称 | ||
| | 純鉄 | 鋼鉄 | 鋳鉄 |
| 炭素量 | 0.02%未満 | 0.02%~2.14% | 2.1%~6.67% |
鉄鋼とは
鉄鋼は、一般に鉄を主成分とした材料の総称として用いられますが、厳密には鉄に炭素を2%以下の範囲で含む合金を指します。
鉄鋼に含まれる主な成分は炭素(C)であり、これにシリコン(Si)、マンガン(Mn)、リン(P)、硫黄(S)が補助的に加えられます。これら5つの元素は「鉄鋼の五大元素」と呼ばれ、鉄鋼の化学組成の大部分を占めています。
現在、世界で流通する金属材料のうち、重量換算で95%以上が鉄鋼であり、その種類は実に多岐にわたります。
以下に、代表的な鉄鋼素材の種類について解説します。
| 鉄鋼 | |||||
| 炭素鋼 | SPC材(冷間圧延鋼板) | 合金鋼 | ステンレス鋼 | 鋳鉄 | 球状黒鉛鋳鉄 |
| SS材(一般構造用圧延鋼材) | ハイテン鋼 | ねずみ鋳鉄 | |||
| S-C材(機械構造用炭素鋼鋼材) | 合金工具鋼 | 可鍛鋳鉄 | |||
| SK材(炭素工具鋼鋼材) | 機械構造用合金鋼 | | | ||
| | | 超硬合金鋼 | | | |
1.炭素鋼
炭素を0.02%〜2%含む鉄と炭素の合金は「炭素鋼」と呼ばれます。鉄と炭素を主成分とし、ケイ素・マンガン・リン・硫黄・銅も含まれています。炭素鋼はJIS規格によって炭素量に応じて細かく分類されています。
| 炭素含有量 | JISの呼称 | 日本語名称 |
| ~0.1% | SPC材 | 冷間圧延鋼板 |
| 0.1~0.3% | SS材 | 一般構造用圧延鋼材 |
| 0.1~0.6% | S-C材 | 機械構造用炭素鋼鋼材 |
| 0.6~1.5% | SK材 | 炭素工具鋼鋼材 |
1-1.SPC材
冷間圧延鋼板であるSPC材は、厚さ0.4〜3.2mmの薄板で構成され、主に板金機械によるプレス加工や曲げ加工用途に用いられます。丸棒や角棒の形状は存在せず、冷蔵庫の外装に見られるような薄板形状が特徴です。なお、SPCは Steel Plate Cold の略称であり、代表的な規格としてSPCC、SPCD、SPCEがあります。SPCCは一般用途向け、SPCDは絞り加工用、SPCEは深絞り加工用として、それぞれプレス加工に適した特性を備えています。
1-2.SS材
一般構造用圧延鋼材であるSS材は、低コストかつ汎用性に優れることから、最も普及している鉄鋼素材です。SSは「Steel Structure(構造用鋼)」の略称であり、丸棒・角棒・鋼板・型鋼など、多様な形状がラインナップされています。品番の後ろに付される3桁の数字は、引っ張り強さの最低保証値を示しており、例えばSS400は引っ張り強さが400〜510N/mm²の範囲にあります。JIS規格ではSS330、SS400、SS490、SS540が規定されており、実務では特にSS400が多用されています。本材は炭素量が0.2%と低いため、焼入れ性はありません。焼入れを行う必要がある場合は、炭素量が0.3%以上の素材を選定する必要があります。その際には、次項で説明するS-C材が適しています。
1-3.S-C材
機械構造用炭素鋼鋼材であるS-C材は、SS材に次ぐ普及率を誇る鉄鋼素材です。「S-C」はSteelおよびCarbonの略称であり、SとCの間に記される2桁の数字は、炭素含有量(質量%)を100倍した数値を示します。例えば、S45Cの場合は炭素量が0.45%であることを意味します。
1-4.SK材
炭素工具鋼材であるSK材は、炭素含有量が0.6〜1.5%の範囲にあり、鋼材の中では最も高い炭素量を有します。硬度および耐摩耗性に優れ、焼入れ後の硬さはおおむね炭素量0.6%程度で上限に達しますが、摩耗抵抗性は炭素量の増加に比例して向上します。「SK」はSteelおよびKougu(工具)の頭文字を取ったもので、続く2桁の数字は炭素含有率の100倍を表し、例えばSK95は炭素量0.95%を意味します。
2.合金鋼
鉄鋼素材における五大元素に加えて、さらに他の金属元素を添加した鋼材を「合金鋼」と呼びます。合金鋼で用いられる添加元素には、クロム(Cr)、ニッケル(Ni)、モリブデン(Mo)、タングステン(W)、コバルト(Co)などが一般的です。合金鋼は炭素鋼に比べて多様な元素を含むため、価格が高く、形状バリエーションも限られることから、炭素鋼で要求性能が満たせない場合に選択されます。以下に、主な合金鋼の種類を示します。
2-1.ステンレス鋼
「ステンレス」は“Stainless”に由来し、「汚れにくく、サビに強い」という意味を持ちます。ステンレス鋼は合金鋼の中でも代表的な材料で、「SUS材」とも呼ばれます。これは五大元素に加えて、ニッケル(Ni)およびクロム(Cr)を含有する合金鋼です。
品名は「SUS」に続く3桁の数字で規定され、クロムおよびニッケルの含有量の違いによって大きく3種類に分類されます。
詳細は下の表をご参照ください。
| 分類 | 代表品種 | 成分 | 磁性 | 耐蝕性 | 価格 |
| 18-8系 | SUS304 | Cr18% Ni8% | 弱 | 高 | 高 |
| 18Cr系 | SUS430 | Cr18% Ni0% | 強 | 中 | 中 |
| 13Cr系 | SUS410 | Cr13% Ni0% | 強 | 低 | 低 |
2-2.合金工具鋼
工具素材として広く用いられる炭素工具鋼(SK材)は、高い硬度を備えていますが、要求される硬度や耐摩耗性がさらに厳しい場合には、合金工具鋼が選択されます。合金工具鋼には、SKS材、SKD材、SKT材の各品種があり、鉄の五大元素に加えて、クロム、タングステン、バナジウムといった合金元素を添加することで、硬度・耐摩耗性・耐熱性を一層向上させています。
2-3.機械構造用合金鋼
機械構造用部品に用いられる鉄鋼素材には炭素鋼と合金鋼がありますが、より高い強度や靭性が要求される場合には合金鋼が採用されます。
両者の最大の相違点は焼入れ性にあり、合金鋼は素材内部まで硬化しやすく、炭素鋼と比較して優れた機械的特性を発揮します。
材料記号は「S」の後に主要合金元素の記号が付与されます。
各品種ごとの化学成分は下の表の通りです。
| 分類 | 成分 | |||
| Cr | Mn | Ni | Mo | |
| SCr | 0.9~1.2% | 0.6~0.85% | – | – |
| SCM | 0.9~1.2% | 0.3~1% | – | 0.15~0.3% |
| SNC | 0.2~0.5% | 0.35~0.8% | 2~2.5% | – |
2-4.超硬合金
超硬合金は、その名称が示す通り、非常に高い硬度を有する合金鋼です。クロム(Cr)、タングステン(W)、モリブデン(Mo)、チタン(Ti)、ジルコニウム(Zr)、ハフニウム(Hf)、バナジウム(V)、ニオブ(Nb)、タンタル(Ta)などの硬質金属を、鉄(Fe)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)を母材として結合させた合金です。代表的な使用例としては、スローアウェイタイプの旋盤工具用チップに利用されています。
2-5.ハイテン鋼
ハイテン鋼(高張力鋼)は、引っ張り強度が極めて高い特性を持つ鋼材です。汎用炭素鋼であるSS400の最低引っ張り強さが400N/mm²であるのに対し、ハイテン鋼はこれを大きく上回る強度を発揮します。その高い強度と薄さを両立できる特性から、電車車両のボディ、ガスタンク、側溝用排水蓋などに使用されています。
3.鋳鉄
鋳鉄の中でも、炭素を2.1%〜6.67%と多く含むものは「鋳鉄」と呼ばれ、他の鉄に比べて硬い性質があります。その硬さを活かして、自動車部品やマンホール、家庭用の鍋などに広く利用されています。鋳鉄にはいくつか種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
3-1.球状黒鉛鋳鉄
「ダクタイル鋳鉄」とも呼ばれる球状黒鉛鋳鉄は、優れた靱性と高い強度を兼ね備えた材料です。硬さが求められる自動車部品、水道管、車道用マンホール蓋など、多様な用途に適しています。
3-2.片状黒鉛鋳鉄
片状黒鉛鋳鉄は、破面の見た目から「ねずみ鋳鉄」とも呼ばれ、一定の硬さは持つものの、靱性が低く脆いのが特徴です。強度がそこまで求められない歩道用マンホール蓋などに使用されます。
3-3.可鍛鋳鉄
可鍛鋳鉄は、叩いても延性を保つことができる鋳鉄で、その性質から「可鍛」と名付けられています。他の鋳鉄と比べて靱性が高く、衝撃に強いため、自動車部品や鉄管継手などに利用されます。
最後に
本編では、金属材料の中でも世界的に最も多用されている鉄鋼について解説しました。鉄鋼は、自動車や鉄道をはじめ、ほぼすべての工業・産業製品に使用されており、現代の生活に不可欠な素材です。実際の素材選定にあたっては、硬度や耐摩耗性などの特性を十分に考慮し、設計要件を満たすかどうか慎重に判断することが求められます。
また、鉄は錆びやすい性質があるため、屋内で保管することを前提に考えなければなりませんし、状況によっては表面処理加工を施す必要があります。用途に見合った鉄を数多くの種類から選ぶことも、鉄の扱いとして非常に重要な作業です。