その仕組みや特徴などをまとめてみました
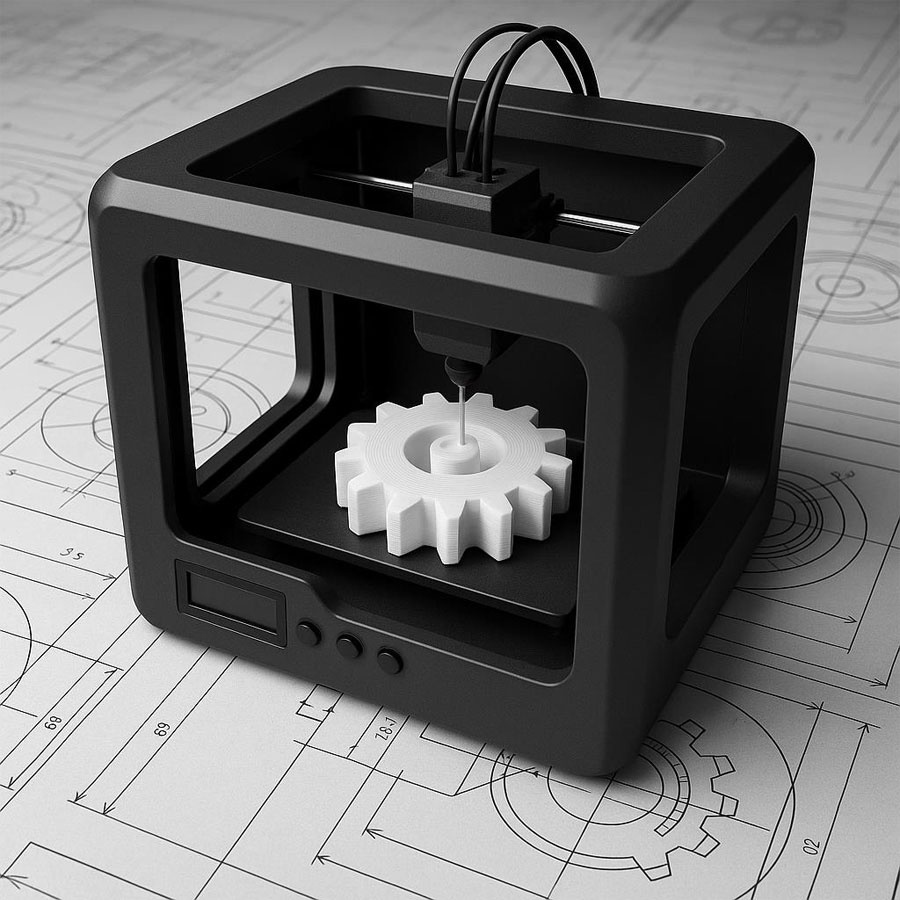
現在主流/熱溶解積層方式
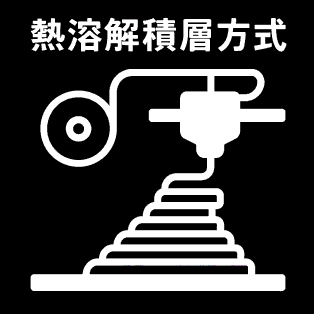
- ISO分類:材料押出法(Material Extrusion)
- その他呼称:FFF方式(Fused Filament Fabrication)
熱溶解積層方式の概要
熱溶解積層方式は、米国Stratasys社が開発した3Dプリント技術で、現在最
も広く普及している方式の一つです。3Dプリンターの主流として、さまざ
まな分野で活用されています。
造形の仕組み
この技術では、熱で溶かした樹脂をノズルから押し出し、ソフトクリーム
を絞り出すように層を一つずつ積み重ねて形を作ります。創業者スコッ
ト・クランプがグルーガンを見たことが着想のきっかけになった、という
有名な話もあります。
特徴と強み
・実際の熱可塑性樹脂を使用可能
熱溶解積層方式の大きな魅力は、ABS樹脂などの本物の熱可塑性樹脂を使
用できる点です。これにより、試作段階でも最終製品に近い物性を持った
部品を製作でき、強度や耐熱性の確認が可能となります。他方式では紫外
線硬化型樹脂が用いられることが多く、実際のABSではなく、「ABSライ
ク樹脂」が代用として使用されることも少なくありません。
・多彩な材料特性に対応
熱溶解積層方式、特に上位モデルでは、エンジニアリングプラスチックや
スーパーエンプラなど、高機能樹脂にも対応しており、特殊な性能が求め
られる製品の造形にも活用できます。
・表面品質の進化
初期の熱溶解積層方式では、積層による段差が目立つという課題がありま
したが、近年ではマシンや材料の進化により、表面の精度も大きく向上し
ています。
課題と弱点
熱溶解積層方式は層を重ねる構造上、積層痕が残りやすいため、表面の滑
らかさやデザイン性を重視する製品にはやや不向きです。こういったケー
スでは、より高精細な造形が可能なインクジェット方式などが適していま
す。また、熱溶解積層単体では金属造形には対応していないため、金属
パーツの造形には専用の金属3Dプリンターが必要になります(ただし、熱
溶解積層と金属粉末を組み合わせた造形技術も一部存在します)。
熱溶解積層方式が利用されやすいシチュエーション
- 製造業におけるラピッドプロトタイピング
- 強度や耐久性が求められる試作部品の製作
- 工具・治具の製造
- 熱可塑性樹脂を使用した最終製品の出力
これらの用途では、熱溶解積層方式の実用性とコストパフォーマンスの高
さが大きな強みとなります。
最も歴史ある3Dプリント技術
光造形方式
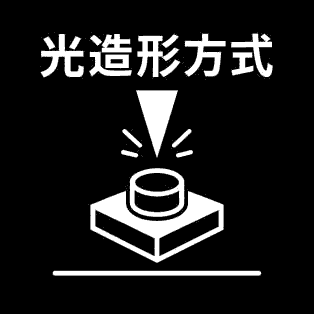
- ISO分類:液槽光重合法(Vat PhotoPolymerization)
- 別名:SLA方式(Stereo Lithography Apparatus)
光造形方式は、3Dプリント技術の中で最も早く開発された方式であり、「SLA方式」とも呼ばれます。さらに、SLAには「レーザー方式」と「DLP方式」という2つの主なバリエーションがあります。
光造形方式の基本構造
この方式では、光硬化性の液体樹脂を使用します。樹脂を満たした槽の中に光を照射し、選択的に硬化させることで、層を重ねて立体物を形成していきます。
主な2つの方式
・レーザー方式
細いレーザー光を1点ずつ走査し、
樹脂を硬化させる手法。
初期から使われている伝統的な方式です。
・DLP方式
プロジェクターのように平面全体に光を一括照射する方式で、広範囲を一度に硬化できるため、造形速度に優れています。ただし、解像度は照射範囲に依存し、サイズが大きくなると精度や表面品質がやや劣る傾向があります。表面には縦横方向に積層痕が出やすい点にも注意が必要です。
特徴と強み
・微細で精密な造形が可能
高い解像度を持ち、滑らかな表面を表現できるため、ディスプレイモデルや造形表現を重視する用途に適しています。
・比較的速い造形速度
特にDLP方式では、層単位で一括硬化できるため、サイズや形状によっては高速に出力できます。
・個人用3Dプリンターも充実
最近では、安価で高精度なデスクトップ型も登場しており、ホビーユースや試作などで広く使われています。
課題と弱点
・耐久性と素材特性
紫外線硬化樹脂は光に弱く、時間と共に黄変や劣化が起こりやすいため、長期間使用する製品や屋外使用には不向きです。
・サイズと構造の制約
一般に吊り下げ式の構造が多く、大型造形や重量物の出力には不向きです。また、変形リスクもあります。
・後処理の煩雑さ
アルコールなどでの洗浄、UVによる二次硬化、サポート除去といった後処理が必要で、手間がかかります。
・高額な産業機種
産業用途では高性能機が必要になり、導入コストが高くなる傾向があります。
高額方式方式が利用されやすいシチュエーション
・デザイン試作やフィギュアなど、見た目の表現を重視する用途
・個人ユーザーや小規模な試作における小型・中型造形
・DDM(デジタル・ダイレクト・マニュファクチャリング)の一部
ただし強度や耐候性が不要なもの
歴史的にはラピッドプロトタイピング用途が中心でしたが、現在は安価なモデルの登場により、個人利用から試作モデルまで幅広く使われています。
表現力に優れた3Dプリント方式
インクジェット方式
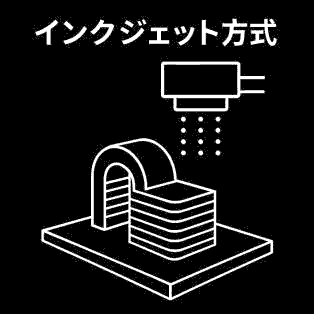
- ISO分類:材料噴射法(Material Jetting)
- 別名:PolyJet方式(Stratasys社)
「インクジェット方式」と呼ばれるこの方式は、正式には「材料噴射法」
に分類されます。仕組みは2Dプリンターのインクジェットに似ており、微
細な材料を噴射しながら、光を当てて硬化させ、層ごとに立体を形成しま
す。高精細な造形が可能で、表面の滑らかさや色の再現性に優れ、視覚的
な表現力を求める分野で高い評価を受けています。
特徴と強み
- 極めて高い表現精度
非常になめらかな仕上がりが得られ、積層痕がほとんど目立ちません。細
部まで精密に表現できるため、製品の外観確認や高品質な試作品の作成に
最適です。 - フルカラー造形が可能
対応機種では複数のカラー材料を組み合わせて、リアルなフルカラー造形
が行えます。後から塗装する必要がなく、デザイン工程の効率化にもつな
がります。上位モデルではPANTONE®カラーに対応し、デザインと完成品
の色差を限りなく縮められます。 - 多素材同時造形
透明素材や柔軟なゴムライク素材を同時に使うことができるため、異なる
質感を1つの造形物で表現することが可能です。アッセンブリを前提とし
た複雑な構造も、一体で造形できます。 - 生地への直接造形にも対応
最新の一部機種では、フェルト、麻、皮革などの布素材に直接プリントす
る技術も登場しています。ファッションやインテリアの分野で注目されて
います。
課題と弱点
・強度・耐久性は限定的
熱溶解積層方式のような熱可塑性樹脂に比べると、機械的強度や耐久性で
は劣ります。紫外線硬化材料のため、時間経過や光の影響で劣化するリス
クもあります。
・コスト面と設備投資
高精細な表現力と多機能性を備えた装置は価格が高めで、導入には一定の
コストがかかります。
インジェクション方式が利用されやすいシチュエーション
・デザイン重視の試作
製品デザインや外観検討を重視する開発段階に最適です。リアルな試作品
を素早く繰り返し作成でき、設計・企画部門における検証が効率化します。
・コンセプトモデルやプレゼン用のモックアップ
色や質感の再現度が高いため、顧客や社内への提案資料としての完成度も
高まります。
インクジェット方式は、まさに「見ること」に特化した3Dプリンティング
技術の代表格です。視覚表現と設計の融合を目指す現場では、その表現力
が大きな力となるでしょう。特にStratasys社の機種はこの分野の先端を
走っており、今後の進化も注目されます。
結合剤で形を作る3Dプリンティング技術
粉末接着方式
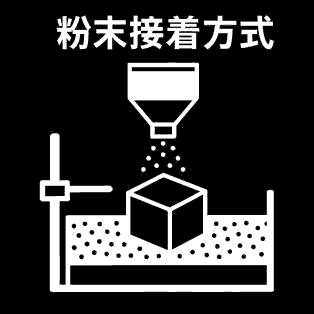
- ISO分類:結合材噴射法(Binder Jetting)
- 別名:バインダージェッティング方式
粉末接着方式は、マテリアルジェッティング(インクジェット方式)が材
料そのものを噴射して積層するのに対し、「結合剤(バインダー)」を噴
射して粉末素材を固めていく造形手法です。当初は石膏を使用した造形に
用いられ、彩色しやすい性質から、フィギュアモデルやコンセプトデザイ
ンの可視化に活用されてきました。その後、技術の進化により金属、樹脂、
セラミックなど多様な素材への応用が可能となっています。この方式を最
初に提案したのはMIT(マサチューセッツ工科大学)の研究者で、現在は
Desktop Metal社にて金属3Dプリンターの開発を進めています。
特徴と強み
- サポート材が不要
造形時にサポート材を使わず、未使用の粉末自体が支持構造の役割を果た
します。これにより複雑な形状も自由に造形でき、除去作業も簡略化され
ます。 - 着色のしやすさ
石膏やその他の材料に直接染料を浸透させるなど、着色がしやすいため、
視覚的な表現が重視されるプロトタイプやモックアップに適しています。 - 高速造形が可能
一層ごとに広い面積を一括で固められるため、比較的速い造形スピードを
実現できます。
課題と弱点
・表面の粗さ
粒状の粉末を固める構造上、表面はやや粗めになり、滑らかさを求める用
途には向きません。
・造形物の強度不足
バインダーで固めただけの状態では脆く、強度が必要な実用部品には不向
きです。後処理で焼結などを行うケースもありますが、その手間と設備コ
ストが課題です。
・粉末の取り扱い
粉末素材は造形後に除去が必要で、飛散防止や粉じん対策も欠かせません。
作業環境や安全性への配慮が求められます。
粉末接着方式が利用されやすいシチュエーション
・デザインの確認やプレゼン用の造形
形状確認や外観評価を目的としたプロトタイピングに適しています。
・彩色が前提のモデル作成
色再現や視覚効果が求められる試作品・展示用モックなどに有効です。
・大量試作に向けた速度重視の用途
高速な出力が求められる場面でも有用です。
粉末接着方式は、「見た目の確認」に特化した用途で真価を発揮する方式
です。機械的特性が重視されない設計・デザインフェーズにおいて、迅速
で柔軟な造形が可能な手段の一つと言えるでしょう。
金属3Dプリンターに革新をもたらした
BMD方式
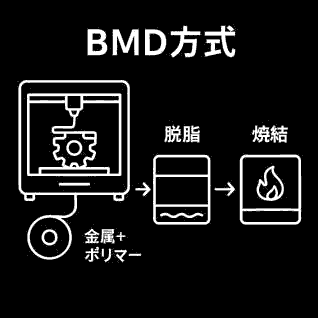
- 英語表記:Bound Metal Deposition(BMD)
- ISO分類:-(未分類)
- 別名:ADAM方式(Atomic Diffusion Additive Manufacturing)
BMD方式は、従来の金属3Dプリンターが抱えていた「取り扱いの難しさ」や「高い導入コスト」といった課題を大きく改善した画期的な金属造形技術です。
BMD方式の造形プロセス
この方式では、以下の3ステップで金属部品を造形します。
- 3Dプリントによる積層造形
ポリマーとワックスで結合された金属粉末を熱で溶かし、熱溶解積層方式のように層を積み上げて立体物を造形します。この時点ではまだ完成品としての強度や特性は十分ではありません。 - 脱脂工程
造形物からバインダー(ポリマーやワックス)を専用装置で除去します。最近では、有機溶剤を使わずに脱脂できる新しいタイプの装置も登場しており、運用性が向上しています。 - 焼結工程
最後に、約1400℃の高温で焼結し、金属を焼き固めることで最終的な部品となります。この工程は、粉末射出成形(MIM:Metal Injection Molding)の技術を応用しています。この3工程を行うプリンター本体・脱脂装置・焼結炉がセットになっており、ひとつのシステムとして提供されます。
特徴と強み
・専用の防爆施設が不要
金属粉末をバラで扱わないため、従来の金属3Dプリンターに必要だった防塵・防爆・不活性ガス環境が不要になります。これにより、大幅なコスト削減と設置場所の自由度が得られます。
・複雑形状の造形に強い
熱溶解積層方式を応用しているため、従来工法では難しかった内部構造や複雑な形状も精度高く造形可能です。
・導入障壁の低さ
従来方式に比べて設備投資が抑えられ、特別な取り扱いスキルも不要なため、これまで金属3Dプリンターを敬遠していた中小製造業などにも現実的な選択肢となります。
課題と弱点
・焼結工程でのガス使用
焼結時にはガスが必要になり、機種によってはランニングコストに差が出ます。導入前にガス使用量と運用費を確認することが重要です。
・排気対策が必要
脱脂工程で有機成分が揮発するため、局所排気装置の設置が推奨されます。とはいえ、トータルコストは従来方式に比べて圧倒的に低く抑えられます。
BMD方式が利用されやすいシチュエーション
・金属パーツの試作や開発のスピードアップを図りたい場合
・多品種少量の金属部品を効率よく製作したい場合
・コストを抑えて金属3Dプリンティングを導入したい企業様
BMD方式は、金属3Dプリントの敷居を大きく下げ、実用化への現実的な選択肢を提供します。従来の常識を覆すこの技術は、製造現場の新たな武器となるでしょう。
金属3Dプリンターの代表格
パウダーベッド方式
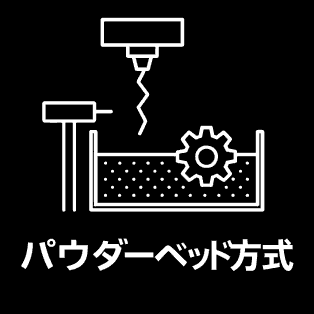
- ISO分類:粉末床溶融結合法(Powder Bed Fusion)
- 別名:PBF方式
パウダーベッド方式は、金属粉末を敷き詰めた床に高エネルギーの光線
を照射し、粉末を焼結・溶融して造形する方式です。かつては金属造形
の主流技術として多くの場面で採用されてきました。この方式には、以
下の2つの熱源方式があります
・レーザー熱源方式(SLM/Selective Laser Melting)
高出力レーザーを用いて選択的に金属粉末を溶かす一般的な方式。
・電子ビーム熱源方式(EBM/Electron Beam Melting)
電子ビームを使って金属粉末を溶融。銅などレーザーでは難しい素材に
も対応可能です。
特長と強み
・高精度な金属造形が可能
金属粉末を直接焼結するため、細かな形状の表現や機械的特性の再現に
優れています。
・多様な金属材料に対応
アルミニウムやチタン、インコネル、さらには銅など、難加工材の造形
にも利用されています。
課題と弱点
・高額な設備投資が必要
装置そのものが高価な上、導入には金属粉の飛散防止、換気・排気・不
活性ガスの管理といった専用施設が不可欠です。
・安全性・環境面の対策が必須
オペレーターが金属粉末を吸い込むリスクや、工場内への粉末の拡散な
ど、安全対策が重要です。
・仕上がりと後処理の課題
造形物の表面はやや粗くなる傾向があり、さらにサポート材の除去など
後処理にも手間がかかります。
パウダーヘッド方式が利用されやすいシチュエーション
現在では、BMD方式のように取り扱いが容易で導入コストを抑えた新技
術も登場しており、まずはBMD方式の適合性を確認することを推奨しま
す。
その上で、以下のようなケースではパウダーベッド方式の検討が有効で
す
- 高精度・高強度な金属部品の造形が必要
- 対象素材がBMD方式では対応できない
- 生産数や運用体制が大規模であり、専用設備を構築できる
パウダーベッド方式は、今なお工業用途での金属造形における定番技術
である一方、運用面でのハードルも高いため、導入には慎重な判断が求
められます。用途や目的に応じて、他方式と併せて検討することが重要
です。
異素材造形に強い積層技術
シート積層法
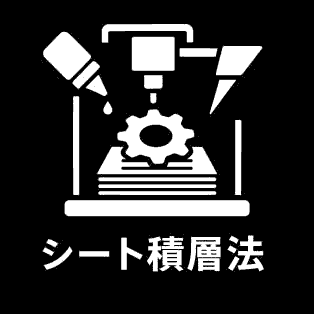
- ISO分類:シート積層法(Sheet Lamination)
シート積層法は、薄い素材シートを1枚ずつ積み重ねて接着し、必要な形
に切り出すことで立体物を作る3Dプリント方式です。接合には接着剤や超
音波溶着などが用いられ、形状の加工にはレーザーやナイフによる切削が
使われます。
特徴と強み
・幅広い素材に対応
紙、PVC(ポリ塩化ビニル)、金属など、他の3Dプリンター方式ではあま
り使われない素材も利用できます。
・異種金属の積層も可能
異なる金属素材を重ねて造形することができるため、機能性を持たせた複
合構造の開発にも活用できます。
課題と弱点
・廃材の発生が多い
シートから輪郭を切り出すため、余分な素材が多く発生しやすく、材料ロ
スが発生します。
・造形精度がやや劣る
他方式と比べて寸法精度や表面品質が劣ることがあり、精密部品の造形に
は不向きな場合があります。
・中空構造の再現が困難
内部に空間を持たせるような複雑な構造を再現するには不向きです。
シート積載法が利用されやすいシチュエーション
・紙やプラスチックシートを使った試作やモックアップ制作
・複数の金属を組み合わせた特性評価用の試作品製造
・比較的単純な外形の造形で、コストや素材特性を重視するケース
シート積層法は、素材の自由度が高く、特定用途に特化した方式です。精
度よりも素材の特性を活かした試作や研究開発の場で、その価値を発揮し
ます。
大型・高耐久造形に強い
指向性エネルギー堆積法(DED)
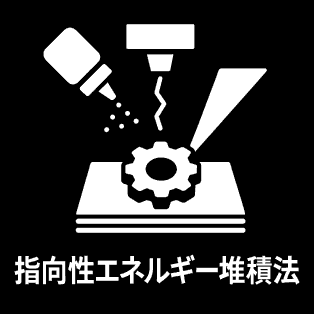
- ISO分類:指向性エネルギー堆積法(Directed Energy Deposition)
- 別名:レーザーデポジション/LMD(Laser Metal Deposition)
指向性エネルギー堆積法(DED)は、金属粉末をノズルから吹き付けな
がら、同時に高出力レーザーを照射してその場で金属を溶融・堆積し
ていく造形手法です。一種の金属の肉盛り溶接技術としても知られて
おり、部品の修復や大型造形に適した方式です。
特徴と強み
・金属材料による高強度な造形が可能
レーザーで高温溶融させるため、造形物は優れた耐久性を持ちます。
・異なる金属材料の組み合わせが可能
異種材料を積層することで、母材とは異なる機能を持つ部品の製作が
可能です(例:硬化層の形成など)。
・大型部品の造形や肉盛り修復に最適
造形サイズの制限が少なく、溶接技術を応用して既存部品の再生・補
修にも用いられています。
・比較的高速な造形が可能
他の金属造形方式と比較して、堆積速度が速く、時間効率に優れてい
ます。
課題と弱点
・金属粉末の安全管理が必要
粉末の飛散や吸入リスクがあるため、運用には防爆・防塵などの設備
や教育が求められます。
・表面品質は粗め
積層後の表面は滑らかとは言えず、仕上げ加工(切削や研磨)が前提
となることが多いです。
・形状の自由度に制限あり
ノズルとレーザーの物理的な干渉や肉盛りの特性上、複雑な内部構造
やアンダーカット形状の造形には不向きです。
指向性エネルギー堆積法が利用されやすいシチュエーション
まずは取り扱いが容易で導入コストも抑えられるBMD方式(金属熱溶
解積層方式)の適用を検討し、以下のようなケースではDED方式を視野
に入れるのが有効です
・既存金属部品の補修や肉盛りが必要な場合
・大型かつ高強度な金属部品の造形を行いたい場合
・異種金属の組み合わせによる機能部品を製作したい場合
指向性エネルギー堆積法は、生産現場での「補修・再生」や「高機能
部材の製造」といった応用分野で真価を発揮する方式です。特に高い
耐久性や素材機能の切り替えが求められる場合に、有力な選択肢とな
ります。